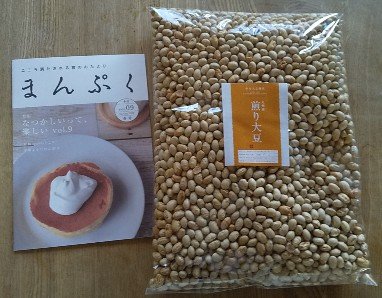ビタミンやミネラルはなるべく食事からとりたいと思う管理栄養士のきぶんやママです。
ビタミンやミネラルは、私たちの健康維持に欠かせない栄養素です。常に不足していないか気になるという人も多いのではないでしょうか。
しかし、これらの栄養素をどのくらい摂取すれば良いのか、その基準はどのように決められているのかを知っているのは栄養士くらいのものと思います。
そこで、この記事では公的機関が定めるビタミン・ミネラルの摂取基準の策定プロセスについて詳しく解説します。
ビタミン・ミネラルに関心のある人におすすめの記事です。
※2025年3月15日更新
日本人の食事摂取基準とは

日本人がとりたいビタミンやミネラルの量は、厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」によって決められています。
この基準は、国民が健康的に生活できるよう、摂取することが望ましいとされるエネルギーおよび各種栄養素の量を示すものです。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、健康の保持・増進、生活習慣病の発症・重症化予防に加え、高齢者の低栄養予防・フレイル予防も視野に入れて策定されています。
5年ごとに改定されるので、次に出るのは2025年版ということになります。
◆厚生労働省:「日本人の食事摂取基準2025年版」策定検討会報告書
目標量だけが決められているのではない

各栄養素のとりたい量、つまり「目標量」だけが決められているわけではありません。
昨今では、サプリメントで手軽に栄養をとろうとする人も増えている中で、摂りすぎによる過剰症の問題も増えてきています。
そこで、欠乏症だけでなく過剰摂取も防ぐことができるように、「摂取量の範囲」(上限も)を決めています。
具体的には、以下のように設定されています。
【エネルギーについて】推定エネルギー必要量
【栄養素について】 推定平均必要量、推奨量
【科学的根拠が得られない場合】 目安量
【生活習慣病予防のため】当面の目標とすべき摂取量や、その範囲を示す目標量
【過剰症を防ぐため】 耐容上限量
ビタミン・ミネラルの摂取基準策定の具体例

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」での、ビタミン・ミネラルの摂取基準策定の具体例をいくつか紹介します。
ビタミンD
脂溶性ビタミンの一つであるビタミンDの目安量は、従来は健康人の摂取の中央値に基づいていました。
しかし、近年、ビタミンD欠乏や不足者の割合が非常に高いことが明らかとなり、「骨折予防に必要な量-日照による産生量」に基づいて目安量が設定されるようになりました。
葉酸
水溶性ビタミンである葉酸は、食事性葉酸と狭義の葉酸の区別が明記されました。葉酸もサプリメントからとる人が多くなっている栄養素の一つですよね。
これにより、葉酸の摂取源や形態に応じた適切な摂取基準が設定されています。
ナトリウム(食塩相当量)
ナトリウムの目標量(上限)は、高血圧や慢性腎臓病の発症予防のため、望ましい摂取量(5g/日)と日本人の平均摂取量の中間値に基づき、男性は7.5g/日未満、女性は6.5g/日未満と設定されました。
さらに、これらの疾患の重症化予防のための目標量(6g/日未満)も定められています。
◆参考:日本人の食事摂取基準2020年版におけるビタミン・ミネラル 田中清 上西一弘
策定は結構大変!科学的根拠と課題

ビタミンやミネラルの摂取基準は、最新の科学的研究や国民の健康状態、食生活の実態など、多岐にわたる情報を総合的に評価して策定されます。
しかし、ヒトを対象としたエビデンスが少ない栄養素も存在し、特に日本人を対象とした研究が不足している場合もあります。
そのため、今後は日本人に適した栄養素の摂取基準を策定するための研究が必要とされています。
こどもの所要量は大人の1/3?
私は栄養大学に通っていたころ、「こどもの所要量は大人の1/3」という目安を聞いたことがありました。
この考え方の背景には、こどもの体重が成人のおよそ1/3程度であることが関係しています。
また、薬の投与量を体重比例で求める時に、簡易的に「成人量の1/3」という目安を使うことがあるようです。
その考えが食事や栄養素の摂取量にも転用され、一部で広まった可能性があります。
ただこの考え方は、一部の栄養素において使われる目安の一つですが、すべての栄養素に当てはまるわけではなく、科学的な根拠に基づいた正式な基準ではありません。
実際のこどもの栄養所要量の決め方
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、年齢ごとに細かく推奨量が設定されています。「大人の1/3量」といった単純な基準ではなく、成長発育の度合いや代謝の違いを考慮して決められています。
例えば、ビタミンCの推奨量(mg/日)を見てみると
| 年齢 | 推奨量(mg/日) |
|---|---|
| 1~2歳 | 40 mg |
| 3~5歳 | 50 mg |
| 6~7歳 | 60 mg |
| 12~14歳 | 100 mg |
| 成人(男性) | 100 mg |
このように、単純に1/3ではなく、年齢ごとに異なる数値が設定されています。
まとめ
ビタミンやミネラルの摂取基準は、国民の健康維持と生活習慣病の予防を目的として、公的機関が最新の科学的根拠や国民の健康状態を踏まえて策定しています。
これらの基準は5年ごとに見直され、私たちが適切な栄養摂取を行うための指針となっています。
ビタミン・ミネラルの不足が気になってサプリメントを服用している人も多いと思いますが、とりすぎによる過剰症も気をつけなければなりません。
食事からビタミン・ミネラルをとって、過剰症になることはまれであるため、なるべく食事からとるようにしながら、本当に不足している栄養素に限ってサプリメントを服用するスタイルを心がけて欲しいと思います。