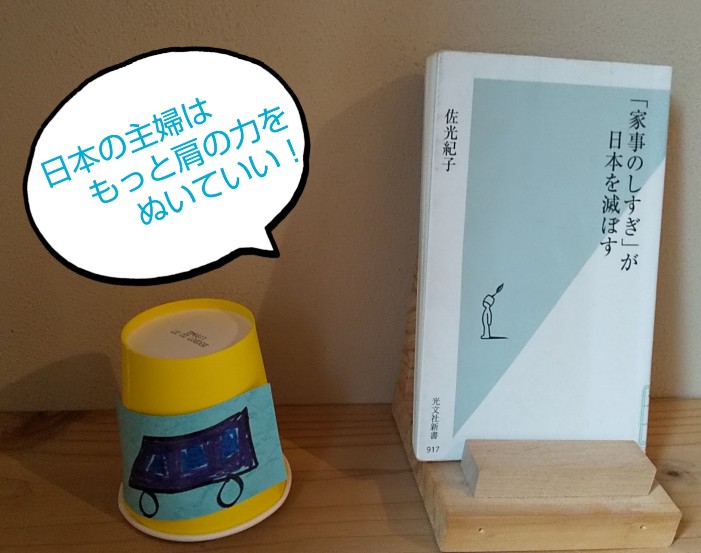ていねいな暮らしにいつも憧れてきた、きぶんやママです。
図書館に行くとそういう本ばかり借りていました。ところが、「家事のしすぎが日本を滅ぼす」という本をたまたま手にとり、考え方が偏っていたかもと思いました。
その本には、なんと「ていねいな暮らし」は女中がいるような裕福な人が、女中に指示出しをするための基準だったと解説されていたのです。
また、「家事を外注する暮らし」を新しく提案してくれるものでもありました。
もちろん、「ていねいな暮らし」を実践することを否定するわけではありません。そういう暮らしが好きな人もいるし、(私も割合好きなのです)それは人それぞれの価値観で違っていて良いのです。
ただ、仕事をしながら「ていねいな暮らし」が実践できないと悩む必要はないということです。
女中に指示出しをするための基準とはどういうことか?「家事を外注する暮らし」というのはどういうものか?海外に住む私の友人ママの様子も紹介しながら解説したいと思います。※2025年3月21日更新
「ていねいな暮らし」で頭を悩ます人におすすめの記事です。
●参考にした本:「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光紀子著 光文社新書
「ていねいな暮らし」は「女中のいる家」の基準だった!?

「ていねいな暮らし」というと、どういう生活を想像しますか?
料理はいつも手作り、重曹などの自然素材で掃除をする、食事で使えるハーブを育てる…そんな生活が私の考える「ていねいな暮らし」です。丁寧に家事をする毎日というイメージですね。
しかし、明治時代の教科書では、そうした「ていねいな家事」は自分で全てやりましょうという意味ではなく、きちんと使用人に指図できるように教育されていたのだそうです。
つまり、私たちが考えるような「ていねいな暮らし」や「女中のいる家」の基準だったというから驚きです。
明治時代の教科書に紹介されている家事
明治41年の高等女学校教科書では、これから主婦になる女学生たちに家事全般を教えるために、以下の家事を教えるページがありました。
- 衣食住
- 育児
- 養老(介護のことだと思います)
- 看病
- 一家の管理(ここに使用人の管理も含まれている)
- 家計の管理
いわゆる、私たち主婦が今現在やっている家事そのものです。これを一通り学び、それをきちんと女中に指示してやってもらいましょう、ということなのですね。
学校の教科書なら、女中がいないような普通の子も通っていたから、女中ありきの内容ではないでしょう?と思われるかもしれません。
しかし、当時は経済的によほど恵まれた家庭でないと高等女学校には行けませんでした。
文部科学省の「日本の成長と教育」によると、(中略)当時小学校を卒業した子どもは全国で37万だが、そこから高等女学校へあがった女子は全国で800人しかいない。
「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光紀子著より引用
つまり、一部の恵まれた女子だけ(女中がいるような)がこの教科書を使っていたということになるのです。
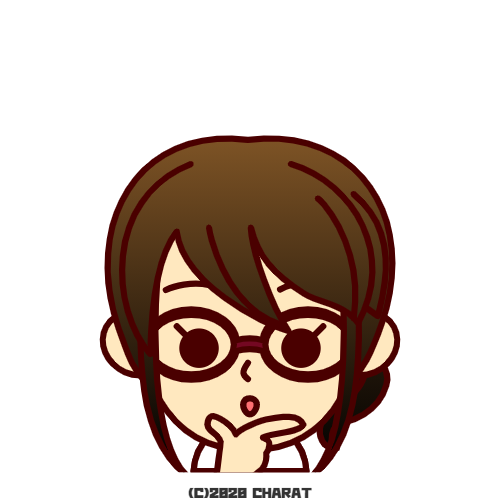
今の主婦は、この家事を一人で請け負っている人ばかりですよね。
例:献立や衣類についてのページ
例えば献立については、「飽きると食欲が落ちるから、同じ食品を続けて使わず、なるべく献立を変えなさい」などの一文があるそう。
衣類については、汚れを見たらすぐに落とすための対策をしましょう、ちりや埃は絹・麻布なら羅紗やフランネルではらい、綿・毛布などはブラッシングしましょうと細かく指示されています。
電化が進んでいない時代にもかかわらず、昔の主婦はもっと細かく掃除をしていたんだなと思ってしまうが、そうではなく、女中に指示を出すための知識でした。
主婦の心得について出てくるのは下女・下男・召使の監督なのである。使用人を使用する目的から始まって、選び方、取り扱い方、給与など、6ページを割いて監督者の心得が書かれている。ちなみに、献立には5ページがあてられているので、「一家の管理」には献立よりも多くのページが割かれていることになる。
これはどういうことかというと、ここに書かれているような家事や、毎日献立が変わる食事のありようは、女中さんを置くような家庭向けの家事だったということだ。
「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光紀子著より引用
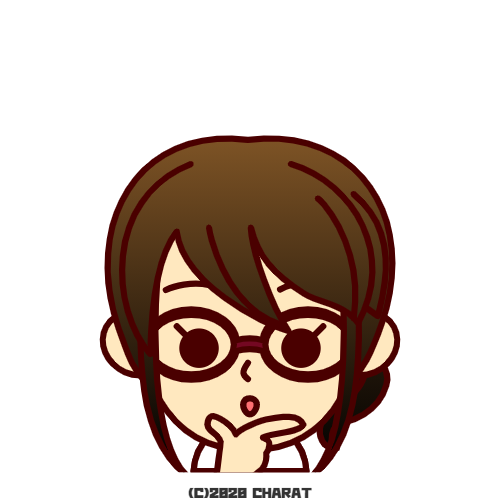
ていねいな暮らしは本当に必須のことなのか?と考えてしまいました
使用人に指示する家事が「ていねいな暮らし」へ

戦後、使用人を抱えるような家庭は減り、核家族化が進行しました。
しかし、流通システムの発達、家電の発達で、使用人がいなくても「毎日違う献立」は作れるし、「毎日きちんと掃除する」ことも「毎日洗濯すること」もできるようになりました。
なぜ女中がいなくてもそうした家事が成り立ったかといえば、女中の役割を専業主婦が引き受けたからにほかなりません。
そうしてきちんと家事をするということが、私が理想としていた「ていねいな暮らし」へと発展しました。
やるべき家事が多いから専業主婦の人気が高い日本

「ていねいな暮らし」を実践するには、家電が発展したとはいえ時間のゆとりが必要でしょう。仕事をしながらすべてを一人で実践するのは大変な話です。
大勢の女中がしていたことを一人ですべてこなそうとするのですから当然です。
だから、日本では世界に類を見ないほど、専業主婦の人気が高いのだそうです。やるべきと思わされている家事が多いのですね。
海外の母は家事を外注して働く人が多い
日本に比べ、海外の母は仕事をしている人が大変多く、そのかわり家事は外注することが多いです。
日本でも最近、お掃除やお片付けを代行してくれるサービスが増えてきました。とても良い傾向だと思います。
私の尊敬する英語の先生はこう言っていました。「私は英語のスキルで貢献する、そのかわり苦手な家事や育児は全部外注する、得意な人がそれぞれを請け負った方が良い結果が得られる」
確かに、そうした方が家事・育児が得意な人は収入を得られるようになります。
また、海外に住む私の友人は、ベビーシッターをたまに導入して夫婦でディナーに行くような話もしていました。
日本の友人は、「私も働いているのに主人やこどもは全然手伝ってくれない」と、仕事のわりふりを家族にしてもらおうと思いがちです。そうではなくて、外注すれば家族間の言い争いも減る気がします。
少し肩の力を抜いて、家事は外注でおまかせし、自分は外に働きに行く。そういうスタイルが一般的な世の中になると、子育てしながらでも働きやすくなるのではと思いました。
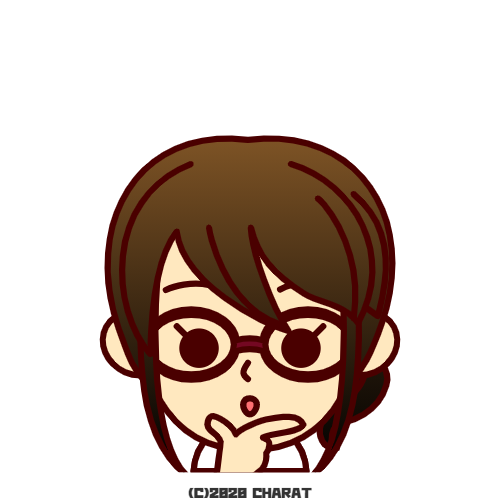
なんでもかんでも母がやるべき、それが当たり前、そういう思い込みが日本人の中には根強くあるようです。
まとめ
家事をきちんとこなすこと、「ていねいな暮らし」を実践することは、歴史を紐解くと、かつての女中の仕事の基準であったことは驚きでしたね。
もちろん、そうすることが好きな人は全く構わないのです。
問題は、それができないと悩んでいる人たちや、仕事をしながら「やるべき家事」が多すぎて困ると思っている人たちのことです。
日本の主婦は「家事は私もしくは家族で割り振って全部やるべき」と思っていることが多いので、もっと仕事を外注しても良いと思います。
その分、自分のスキルを活かした仕事へともっていかないともったいないし、これからの日本には女性の力が必要です。
「ていねいな暮らし」をあまり礼賛しすぎないことも大切ですね。人それぞれの暮らし方があるので。
このブログが、暮らし方を見直す一つのきっかけになってもらえれば幸いです。