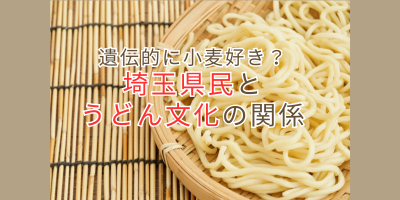最近、小麦グルテンを極力とらないようにしようと誓った、管理栄養士のきぶんやママです。(小麦グルテンが身体に合わない体質の疑い)
しかし、夫は小麦製品が大好きで、米よりもパンやうどん・ラーメンをよく食べます。特にうどんは毎日食べたいと言うほど好きです。
なんでこんなに小麦製品が好きなの?と疑問に思い、調べてみたところ、驚きの事実が分かりました。
なんとその理由が生まれ育った地域にあったのです。主人は埼玉県秩父地方出身なのですが、実は香川県のように、埼玉県もうどん文化がありました。
しかも、埼玉県でうどんが根付いた理由に、「小麦」と「養蚕業」の密接な関係があるかもしれない!ということも分かりました。
今回は、埼玉県とうどん、小麦と養蚕の関係性について調べたことをまとめました。うどん好きな埼玉県民の皆さん、小麦がなぜ好きなのかそのルーツを知りたい人におすすめの記事です。
埼玉県は「うどん県」だった!

「うどん県」と聞くと、真っ先に香川県を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、実は埼玉県もうどん文化が盛んな地域なのです。
驚きのうどん生産量と消費量
令和3年のうどん・そばの生産額の都道府県ランキングでは、なんと埼玉県が第1位でした。
→こちらのページを参考にしました(地域の入れ物:うどん・そばの生産額の都道府県ランキング 令和3年)
生産量だけでなく、消費量も香川県に次ぐ消費量で、「東のうどん県」とも呼ばれているようです。
県内にはうどんのチェーン店も多く、特に「山田うどん」は車で道を走っていてもたくさん目にする、埼玉県発祥のうどんチェーン店。主人もこどもの頃によく食べたと懐かしがるお店です。
武蔵野うどんと小麦栽培
また、埼玉県には「武蔵野うどん」という郷土うどんがあります。地元産の小麦を使った、コシの強いしっかりとした歯ごたえが特徴のうどんです。
◆武蔵野うどんをもっと知りたい人はこちら
Web:武蔵野手打ちうどん保存普及会
東京都小平市~武蔵村山市~埼玉県所沢市~群馬県の辺りで、この「武蔵野うどん」が食べられていたようですが、それは小麦の栽培と密接に関わっていたことに由来しています。
小麦栽培が盛んだった埼玉県

埼玉県では、米の収穫が終わった後の田んぼに小麦を植えて、米と小麦の両方を作っていました。
初夏~秋は米を作り、秋~冬は麦を作れば、同じ土地から多くの収入を得ることができます。そうして田んぼの休眠期を活用して小麦を栽培することを「裏作(うらさく)」と言います。
武蔵野うどんの地域でもある、武蔵野台地と呼ばれる辺りは、火山灰に覆われた関東ローム層の地質で、あまり米を作るのに適さない地域もありました。
そういう場所では特に、小麦やそば、芋などが栽培されました。だから埼玉(群馬寄りの埼玉県秩父地方)出身の主人は小麦が米よりも主役の勢いで食べていたのですね。
主人の祖先はみなその辺り出身の方々だったので、もはや遺伝子で小麦文化が受け継がれているようです。
埼玉県の郷土料理として、「小麦まんじゅう」も有名です。小麦粉を使った皮であんこを包んだもので、地元の家庭で親しまれてきた伝統的な食品です。
農林水産省によると、これも小麦が広く栽培されていた背景と密接に関係しているとされています。
◆農林水産省:うちの郷土料理 小麦まんじゅう 埼玉県
蚕農家と小麦栽培との関係

「昔、そばに蚕を飼っている人がいて、よく蚕を触りに行ったよ」と主人が言っていました。埼玉県で蚕!?と思いましたが、埼玉県秩父地方も、かつて養蚕業が盛んでした。
そういえば、お隣の群馬県も養蚕業が盛んで、蚕が作る絹で糸を古くから作っています。世界遺産にもなった富岡製糸場は群馬県にありますよね。
主人の故郷は群馬寄りの埼玉県なので確かにそのような地域だったのでしょう。
そこで、もしかしたら蚕農家も小麦を栽培していたのでは?と思い調べてみました。
すると、米農家と同じで桑畑(蚕のエサ)の裏作として麦が作らていたことが分かりました。
養蚕には桑畑が必要ですが、蚕の生育が終わると畑を利用して別の作物を育てて収入を得る必要がありました。その代表的な作物が小麦だったのです。
◆一橋大学の研究論文にその内容が記されていました。
「稲麦・養蚕複合経営の史的展開」田中 修 日本経済評論社 1990.9
まとめ
夫の小麦好きには何か理由があると調べた結果、埼玉県の意外な一面が発見できました。
埼玉県では、米の裏作として小麦が栽培され、養蚕業でも裏作として小麦の栽培が広がっていた背景がありました。そしてうどんなどの小麦文化が定着しました。
その結果、現在でも多くの埼玉県民が小麦製品を愛しているのですね。夫が小麦好きなのは、偶然ではなく地域の歴史的背景によるものかもしれません。
自分のルーツや食文化を知ると、自分にとっての健康的な食生活がどんなものかわかるかもしれませんね。